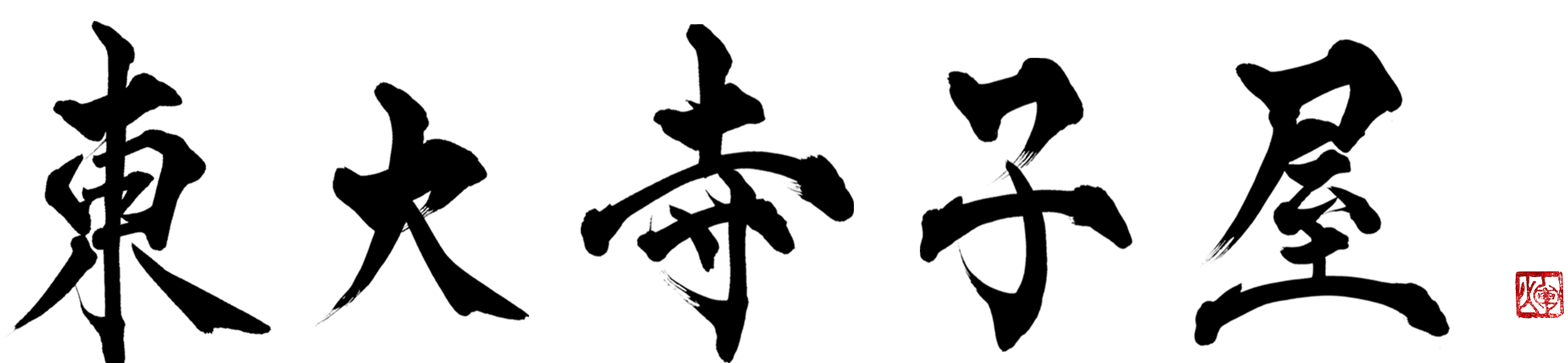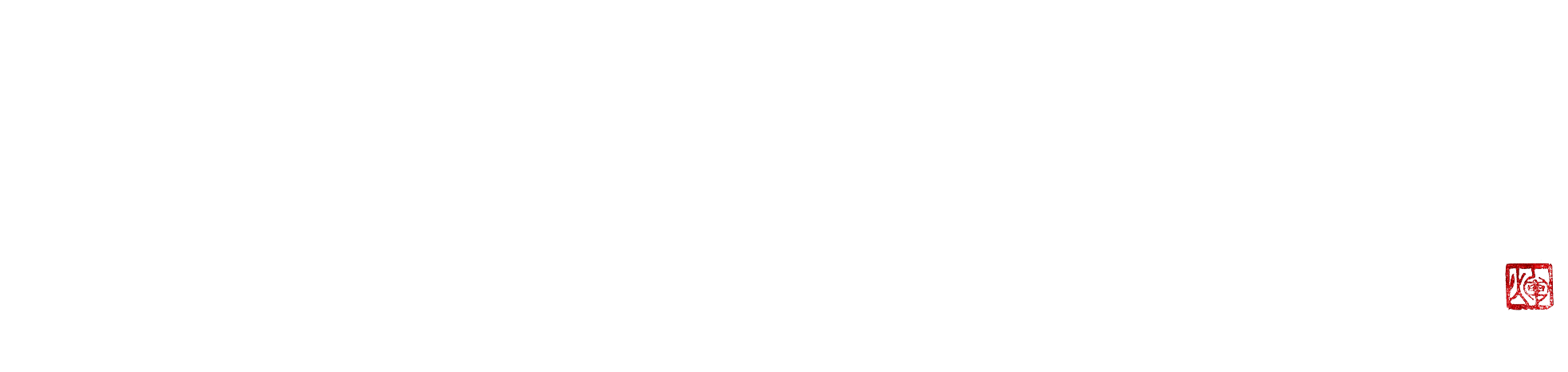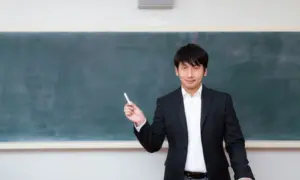はじめに:理科が苦手な中学生へ
「理科って覚えることが多すぎる」「公式は暗記しても、問題になると解けない」「生物や地学はまだ好きだけど、物理と化学は苦手」——そんな悩みを持つ中学生はとても多いです。
理科という科目は、「暗記」と「理解」のバランスが大切で、それぞれの分野に合った学習法が必要です。
そこでこの記事では、理科一類に合格した現役東大生ライターの「けんけん」が、中学生が理科を効率よく学び、定期テストや高校受験で得点を取るための勉強方法を分野ごとに詳しく解説します!
苦手意識をなくし、理科を“楽しく、得点しやすい教科”に変える第一歩にしてください!
理科という教科の特徴をつかもう
理科は中学校で大きく分けて4つの単元に分かれています。
物理:計算と公式がカギ
力や運動、電流や音・光などの単元です。
数字を使った計算問題が出るため、苦手と感じる生徒も多いですが、実は「公式の意味を理解しながら練習する」ことで誰でも得意になれます。
化学:実験+知識をつなぐ力
気体の性質、化学反応、イオン、物質の変化などを扱います。
実験結果を元にした問題が多いため、「ただの暗記」では太刀打ちできません。実験の意味と反応のしくみを理解するのがカギです。
生物:暗記だけではなく流れをつかむ
体のつくりや働き、植物、細胞、遺伝などが中心です。
一見、暗記だけでいけそうですが、「仕組み」や「流れ」を理解して覚えることで、ずっと記憶に残りやすくなります。
地学:自然の変化を論理的にとらえる
天気、地層、火山、天体など、日常生活やニュースと結びつきやすい単元です。
図やグラフを読み取る力が求められることが多いので、普段から図を見る習慣をつけておくと◎。

勉強の基本ステップ:全分野に共通する進め方
教科書を使いこなす
理科の勉強で一番大事なのは、「教科書の内容をしっかり理解すること」です!
教科書に出てくる太字の用語、図やグラフ、実験の手順や結果はすべて重要事項。
授業中の先生の説明と照らし合わせながら、読んだり、ノートにまとめたりしましょう。
「覚えなきゃ」と思うより、「どうしてそうなるの?」と疑問を持って読んでいくことで、自然と記憶に残りやすくなります。
ノートまとめは「自分の言葉で書く」
理科ノートを取るとき、ただ板書を写すだけでは意味がありません!
図や表は自分で手書きし、用語の説明もできるだけ「自分の言葉」でまとめましょう。
一度自分の頭の中で噛み砕いてから書き出すことで、理解が深まります。
分野別:中学生の理科の勉強法
物理の勉強法:公式の暗記ではなく「理解」が大事
力のつり合い、速さ、電流、電圧など、公式を使う問題が多い物理。
まずやるべきは、公式の意味を理解することです。たとえば「速さ=距離÷時間」という式を、実際の生活で使えるようにイメージしてみましょう。
「家から学校まで2km、15分かかったら、速さは…?」と、身近な例を自分でつくって練習するのが効果的です。
また、単位にも注意が必要です。「m/s」や「N(ニュートン)」といった理科特有の単位は、問題でよく引っかかります。普段から答えに単位をつけるクセをつけましょう。
苦手な人は、まず基本問題を繰り返し解くこと。いきなり難しい問題に挑まず、教科書の確認問題や学校のワークから始めて、自信を積み上げていきましょう。
化学の勉強法:実験を“映像”でイメージしよう
化学は、実験とその結果をどう読み取るかがポイントになります!
まず、教科書に出てくる実験の手順や反応を、頭の中で動画のように思い浮かべるようにしましょう。
たとえば「水に塩酸を加えてマグネシウムを入れると…?」という問題が出たら、どんな泡が出るのか、試験管の中がどう変化するのかを想像します。
イオンや中和、質量保存など抽象的なテーマは、図やモデルを使って説明されているページを重点的に読みましょう。
また、「言葉だけで覚える」のではなく、「図や式とセットで理解する」ことが大切です。
生物の勉強法:流れで覚える・図とセットで暗記する
細胞の構造や消化、血液の流れなど、生物分野は「流れを覚える」ことがカギです!
たとえば、消化の仕組みを覚えるときは、「口→胃→小腸→大腸→肛門」という順番だけでなく、どこでどの酵素が働くのか、どんな栄養が吸収されるのかをセットで整理します。
また、植物のしくみや分類、光合成・呼吸などの単元は、図や表といっしょに覚えると定着しやすくなります。
図に書き込みながら覚える、白紙に自分で図を再現するなどのアウトプット練習も効果的です。
地学の勉強法:グラフや図を読めるようになろう
天気図、地層の断面図、惑星の動きなど、地学分野は「図の読み取り力」が必要です。
ただ用語を覚えるだけでなく、「図から何が読み取れるか」「変化の法則は何か」を考えるようにしましょう!
天気や季節の変化などは、ニュースや天気予報を見るときにちょっと気をつけて見るだけでも自然に知識が増えていきます。
また、星や宇宙に関する内容も、自分で星座を見たり、アプリで夜空を観察したりすることで、実感を持って覚えることができます。



テスト・受験対策に向けての勉強法
中学生にとって理科の定期テストや高校受験は、学んできた知識を成果として発揮する重要な場面です!普段の勉強方法と、テスト前・受験前の勉強方法には少し違いがあります。ここでは、テストや受験に向けて成果を出すための具体的な勉強法を解説していきます。
テスト数日前から「復習モード」に切り替える
テストや受験が近づいたら、まずやるべきは「新しいことを無理に詰め込む」のではなく、これまでに学んだ内容を確実に定着させることです!
学校のワークや問題集で間違えた問題に印をつけておき、それをもう一度やり直す「復習中心」の勉強に切り替えましょう。
特に理科は、単元ごとの知識が積み重なる教科なので、苦手な単元は前の学年にさかのぼって確認することも大切です。
「わかったつもり」をなくすためにアウトプット重視
理科に限らず、すべての勉強に共通することですが、「読む」「見る」だけでは記憶には定着しにくいものです!
理解を定着させるためには、自分の手で書いて、言葉で説明して、問題を解いてみる「アウトプット学習」が重要です。
たとえば、用語の暗記ならノートに何も見ずに書いてみる、計算問題なら途中式を省かずに解いてみるといった工夫が必要です。
特に実験の原理や結果を問われる問題では、頭の中で再現できるかがカギになります。図を書いて流れを説明する練習をすると、記述問題にも強くなります。
問題演習の質とタイミングを意識する
テスト勉強で問題を解くときは、「数をこなす」よりも「1問を丁寧に解き直す」姿勢が大切です!
間違えた問題に対しては、なぜ間違えたのか、どこで勘違いしたのか、知識が足りなかったのかを必ず振り返りましょう。
1度間違えた問題を放置してしまうと、テスト本番でも同じミスを繰り返す可能性が高くなります。
また、時間配分にも注意を。受験前には、過去問や予想問題を実際に時間を計って解いてみる「実戦形式の演習」が非常に効果的です。
時間内にどの順番で解くか、記述問題にどれくらい時間をかけるか、見直しの時間は確保できるかなど、自分なりの戦略を作ることが点数アップにつながります。
自分専用の「ミスノート」を作る
テスト対策の中でも特に効果的なのが、「ミスノート」の活用です!これは、自分が間違えた問題や苦手な用語・公式を1冊のノートにまとめておくものです。
自分だけの弱点集として、テスト直前や受験直前にパッと見返すことができるので、時間がないときでも効率的に復習ができます。
作り方のコツは、ただ問題と答えを書くのではなく、「なぜ間違えたか」「次にどうすれば正解できるか」といったコメントも入れること。
こうすることで、同じミスを繰り返すリスクを大きく減らせます。
私も「ミスノート」を作成し、間違えた個所を見つめなおすことでテストの点数を上げることができました!
このように、テストや受験に向けての理科の勉強では、「復習の徹底」「アウトプット中心の学習」「実戦的な演習」「自分だけのミス対策」がポイントになります。
ただ覚えるだけでなく、「どう問われるか」「どう答えるか」を意識することで、理科は着実に得点源になります。自信を持って取り組めるよう、今日から計画的に勉強を進めていきましょう!
まとめ:理科を味方につけよう!
理科の勉強は、「暗記」+「理解」+「実感」の3つの要素がそろうことで、ぐっと点数が上がります。
中学生のうちに正しい学習法を身につけることで、高校でも理科が得意な教科になります。
まずは教科書を丁寧に読み、実験や図に興味を持ち、基本問題をくり返し解く習慣をつけましょう。
理科は、自然や人間の体の仕組み、宇宙の謎にせまる面白い教科です。
「わかるって楽しい!」という感覚を大切にして、自分なりの理科勉強法を見つけてください。
そうすれば、定期テストでも受験でも、自信を持って得点できるようになりますよ!