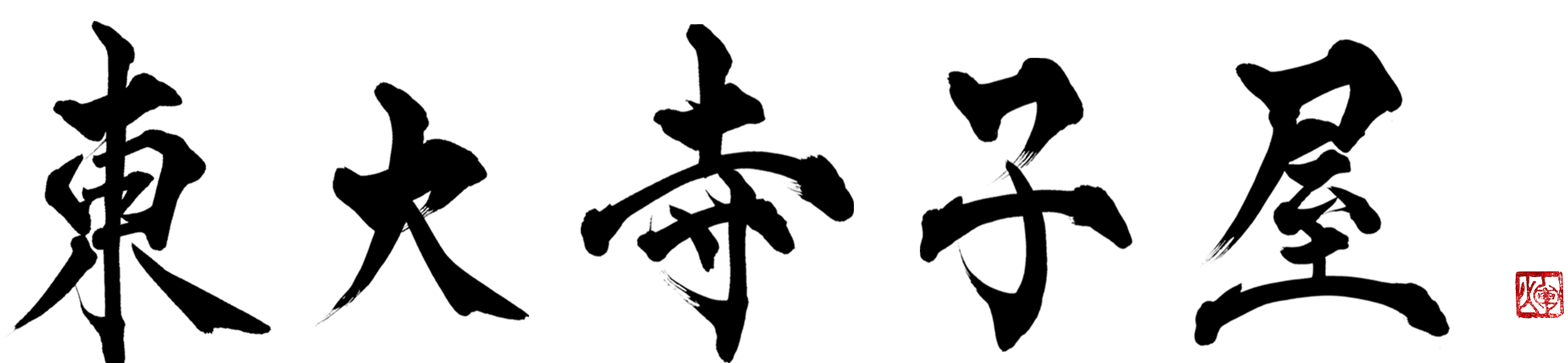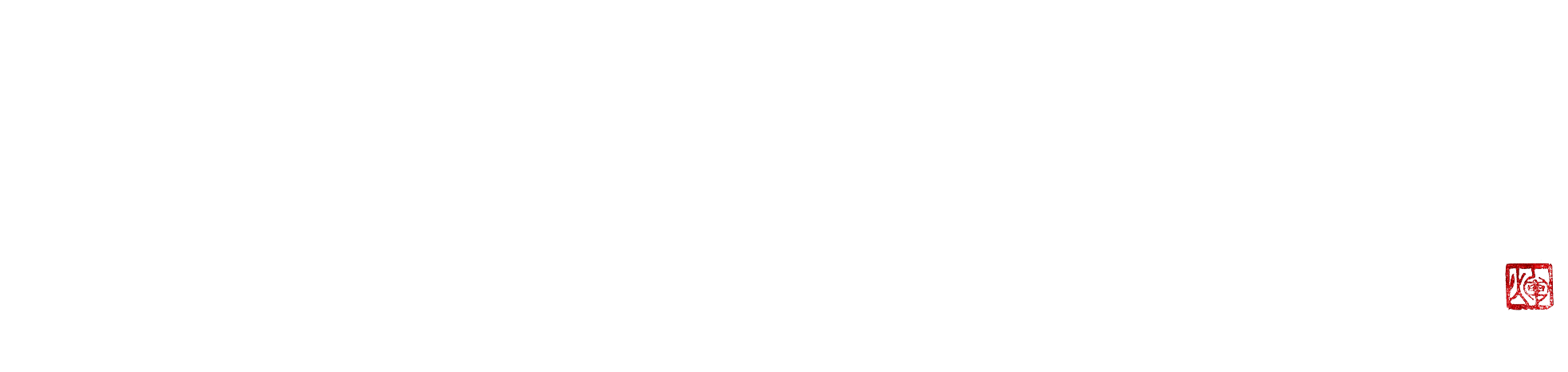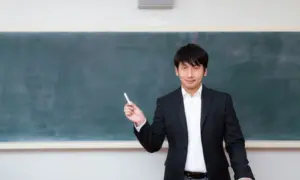はじめに:現代文は「センス」ではない
「現代文はなんとなくで解いてる」「選択肢を選ぶときに感覚でしか分からない」という高校生の声は非常に多いですが、それは大きな誤解です!現代文は“論理的な科目”であり、正しい方法と意識をもって学べば誰でも安定して点数を伸ばせます。
特に大学受験において、現代文は国語の中核を担うだけでなく、他教科の読解力や論理的思考力にも直結する重要な科目です!では、現代文の正しい勉強法とはどのようなものでしょうか?
この記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、基礎から応用まで体系的に紹介していきます!
私も最初はなんとなくで現代文を解いていて、点数が高い時も低い時もあり不安だったのですが、勉強方法を見直して点数が安定するようになりました!現代文が苦手な方、さらに点数を伸ばしたい方は是非参考にしてみてください!
読解力の基礎をつくる:現代文の「読む技術」を習得する
言葉の定義と論理展開を意識する
現代文では「筆者の主張」が何かを正確に把握することが求められます。そのためには、まず文章内で出てくるキーワードの定義に敏感になる必要があります。例えば、「自由」という言葉が本文に登場した場合、その言葉がどのような意味で使われているのかを正確に読み取ることが重要です。
また、接続詞や指示語にも注意を払いましょう!「しかし」「つまり」「たとえば」などの言葉は、文章の論理構造を明らかにしてくれる道しるべです。これらを無視して読んでしまうと、筆者の主張や文章の流れを正しく把握できなくなります。
段落ごとの要旨をまとめながら読む
長文を読むときは、段落ごとに「この段落は何を言っているのか?」を自問しながら読み進めましょう!これは要約力や記述力にもつながる訓練です。実際の問題でメモを取りながら読む必要はありませんが、頭の中で簡潔に内容を整理する意識をもつだけで、読解の精度がぐっと高まります。

現代文の設問対策:選択肢問題と記述問題の攻略法
選択肢問題の正しい解き方
現代文の選択肢問題で多くの受験生が苦戦するのは、「正解の選び方」ではなく「間違いの消し方」にあります!つまり、「どれが合っているか」ではなく、「どれが本文と食い違っているか」を探す視点が重要です。
このためには、本文の該当箇所に戻って読み返すことが不可欠です。
「本文に書いていないことは正解にできない」という鉄則を忘れないようにしましょう。特に似ている選択肢が並んでいるときほど、言葉のニュアンスや筆者の立場に照らして丁寧に吟味することが大切です。
記述問題で減点されない書き方を身につける
記述問題で高得点を取るには、答案に「本文の表現」を適切に盛り込むことがポイントです!自分の言葉に言い換えすぎると、採点者に意図が伝わらず減点されやすくなります。
逆に、本文をそのまま写すだけでもダメです。引用と要約をバランスよく行いながら、論理的に完結した文章にまとめる練習が必要です。
記述の練習には、過去問や記述問題集を使って、実際に手を動かしながら学ぶことが効果的です。最初は制限時間を気にせず、「正確に書くこと」に集中し、徐々に時間配分を意識していくとよいでしょう。
また記述は人に見てもらうのが良いでしょう!私は学校の先生に解いた過去問などの添削をお願いしていました。皆さんも学校や塾の先生に客観的なフィードバックをもらうとよいと思います!
語彙力と背景知識を補強する:読解を支える土台づくり
現代文に必要な語彙を意識的に増やす
現代文では、論理的思考を要する評論文が多く出題されるため、日常会話では使わない抽象的な語彙を理解しているかどうかが重要です。「演繹」「帰納」「構造主義」「実存主義」など、文中に出てきた難語はその場で意味を調べ、ノートなどにまとめておく習慣をつけましょう。
語彙が増えると、文章全体の意味がすっきりと把握できるようになり、選択肢や記述でも正確に対応できるようになります!
思想や社会背景に触れる機会を増やす
現代文のテーマは哲学、社会、教育、医療、環境など多岐にわたります。
これらのトピックについて一定の知識があると、文章の前提が理解しやすくなり、設問に対してもより的確に答えられます。新聞やニュース、NHKの「100分de名著」などを利用して、多様なテーマに触れておくことが実力向上につながります。
問題演習の進め方と参考書の活用法
演習は「量」より「質」で取り組む
多くの問題集を次々にこなすよりも、1冊の良質な問題集を繰り返し使い込む方が効果的です!特に現代文は「答え合わせの後の復習」にこそ力を入れるべきです。なぜその選択肢が正解で、他が違うのかを丁寧に分析することで、読解の視点が磨かれていきます。
おすすめの問題集としては、『入試現代文へのアクセス(基本編・発展編)』『現代文読解力の開発講座』などが挙げられます。解説が丁寧で、復習にも役立つ構成になっているものを選びましょう。
模試や過去問を活用して実戦力をつける
志望校の過去問を早い段階から解くことも重要です。志望大学によって出題傾向や記述の形式が大きく異なるため、本番でのパフォーマンスを最大化するには、実戦的な演習が欠かせません。
過去問演習は「知識の確認」ではなく、「本番の時間感覚」や「実戦での思考力」を鍛える場として活用しましょう。



現代文が苦手な人が最初にすべきこと
現代文が苦手と感じる高校生は非常に多いですが、その理由の多くは「何をどう読めばいいのか分からない」「設問に対する答え方が分からない」といった“読解のルールや方法を知らない”ことにあります!現代文はセンスの科目ではありません。読み方と考え方のルールを一つずつ学んでいけば、誰でも確実に得点源に変えることができます。
まず最初にすべきことは、自分が現代文のどこに苦手意識をもっているかを明確にすることです。
文章を読んでも内容が頭に入ってこないのか、選択肢の違いが分からないのか、記述になるとどう書いていいか分からないのか——このように自分の「つまずきポイント」を分析しましょう。その原因によって、学習の取り組み方も大きく変わってきます。
次に意識すべきは、「現代文の文章はすべて論理で構成されている」という事実です。
感覚で読むのではなく、論理をたどりながら読み解く訓練が必要です。そのためには、まずは短めの評論文などを使って、段落ごとの要旨を頭の中で整理しながら読む練習を始めましょう。たとえば、1つの段落を読んだら「この段落では筆者は何を言いたいのか」を簡潔に言い換えるようにします。そうした「段落単位の要約」を繰り返すことで、文章全体の論理構造が見えてくるようになります。
また、接続語(しかし、だから、たとえば、つまりなど)や指示語(これ、それ、あれ、そのような、など)に着目して読解する癖をつけましょう。これらは筆者の思考の流れや、文と文の関係性を明らかにする重要な手がかりです。たとえば「しかし」が出てきたら、それ以前と以後で対比があること、「つまり」が出てきたらまとめや言い換えがなされていることを意識して読んでみてください。
語彙力不足が原因で読めない場合も多いです。
現代文でよく出てくる抽象的なキーワードや専門的な概念に対する理解が浅いと、文章の意味そのものがぼやけてしまいます。そうした語彙に出会ったときはそのまま読み飛ばすのではなく、意味を調べてノートにまとめておくと効果的です。たとえば、「相対主義」「自己同一性」「価値観の多様化」など、難解に思える言葉も、自分の言葉で説明できるようにしておくと読解がぐっと楽になります。
問題演習では、ただ正解を確認するだけでなく、「なぜ他の選択肢が違うのか」「正解はどのような根拠に基づいているのか」を徹底的に分析しましょう。
特に間違えた問題は、自分の思考と正解の間にどんなズレがあったのかを探ることが重要です。復習ノートを作ることで、同じミスを繰り返さない仕組みができます。
最後に、現代文の苦手意識を克服するためには、焦らず段階的に学ぶことがカギです。
一度で文章全体を完璧に理解しようとせず、まずは1段落、1設問から丁寧に向き合いましょう。そして自分の読み方がどこでズレているのかを確認しながら、徐々に文章全体を見通す力を育てていくことが大切です。
苦手な人ほど、「なんとなく」から「根拠を持って読む」読解へと意識を変えるだけで、見違えるように成績が伸びます。現代文は最も成長が見えやすい科目のひとつ。正しい読み方を学ぶことで、確かな自信につながっていきます。
まとめ:現代文は“武器”になる
現代文はセンスではなく、努力と方法で確実に伸びる科目です!そして、その力は受験勉強にとどまらず、大学の講義や論文、社会に出た後の文章理解力にまでつながります。
論理的に読むこと、正確に書くこと、それらを習慣化すること。これらを継続することで、現代文は誰にとっても「得点源」となり、志望校合格の大きな武器となります。
今この瞬間から、正しい勉強法で、現代文の力を着実に育てていきましょう・・・!
また数学や英語についても記事を書いているので、そちらも参考にしてみてください!