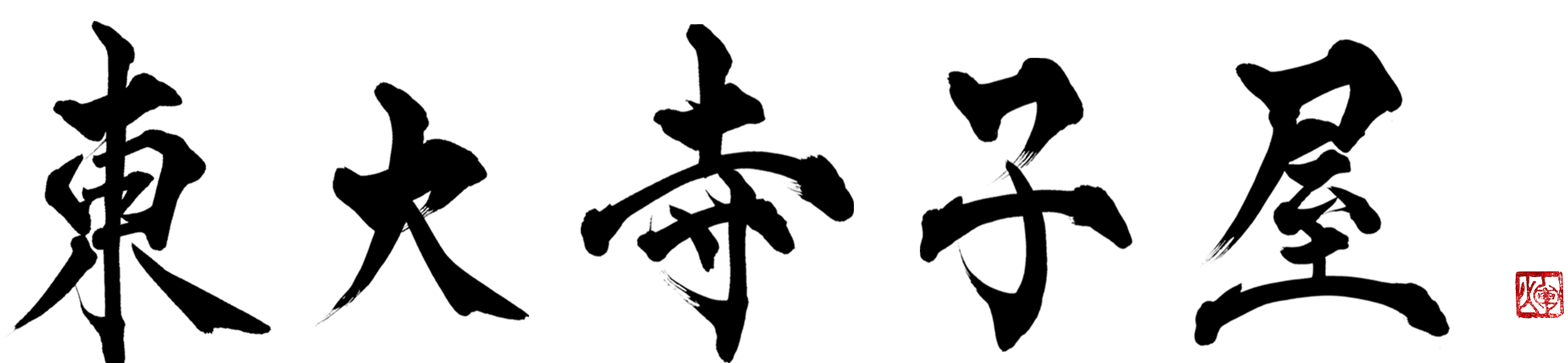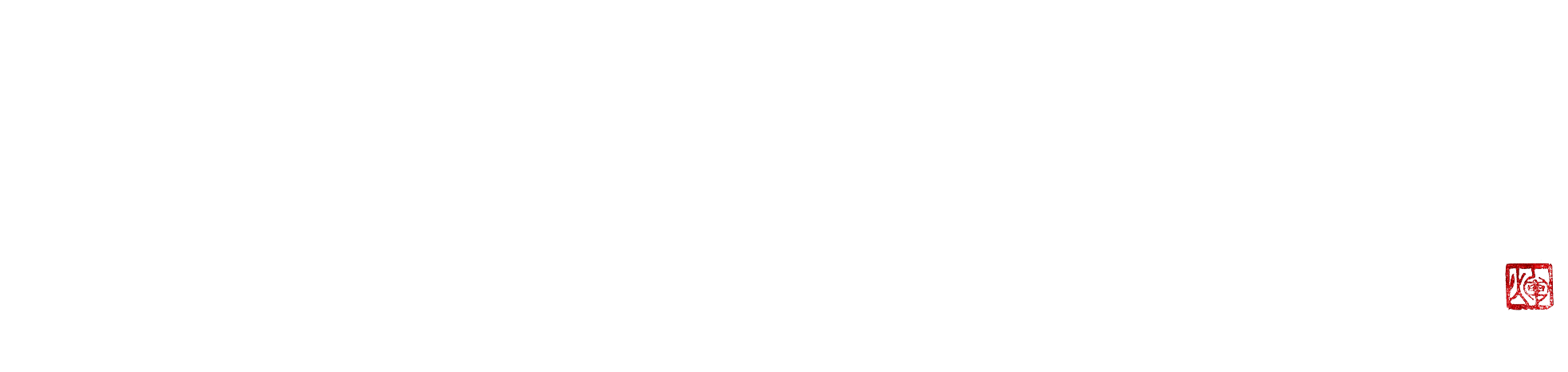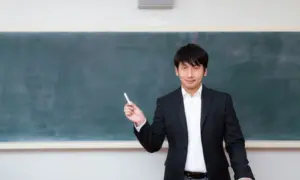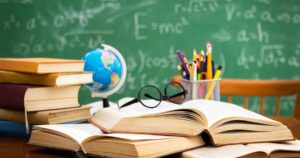はじめに
共通テストや国公立二次試験、私大入試において「倫理・政治経済」は、文系理系を問わず選択する受験生の多い科目のひとつです。暗記科目というイメージが強い一方で、出題傾向や理解の深さによって得点が大きく変動するため、しっかりとした戦略が求められます!
そこでこの記事では、共通テスト倫理・政治経済で98点を取った現役東大生ライターの「けんけん」が、倫理・政治経済を選択する高校生・受験生向けに、効率的で実践的な勉強方法を具体的に紹介していきます!
私は暗記が大の苦手(日本史や世界史から逃げるために理系を選びました・・・)だったのですが、思想の流れや社会との関連を意識することで高得点を取ることができました!暗記だけに頼らない、思考力と理解力をベースにした学習法で、得点源として活用できる力を育てましょう!
倫理・政治経済の特徴と出題傾向
出題範囲の広さと理解の深さが求められる
倫理・政治経済は、「倫理」と「政治・経済」という2つの分野から構成され、それぞれ異なる内容・思考法が要求されます!倫理では哲学や宗教、思想史の流れを学び、政治・経済では現代の制度や理論、時事問題が出題されます。
共通テストでは、選択肢の文章が長文化しており、ただの暗記では対応が難しくなっています。用語の意味や背景を深く理解し、文脈から正解を導けるような読解力も必要です。
倫理の効果的な勉強方法
思想家ごとのストーリーをつかむ
倫理分野では、ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどの古代ギリシア哲学から始まり、近代のカント、ヘーゲル、ニーチェ、そして現代思想まで多くの思想家が登場します!
それぞれの思想家がどのような時代背景の中で、何を考え、どんな理論を展開したのかを「ストーリー」として理解することで、単なる丸暗記から抜け出せます!
例えば、カントの「道徳法則」や「定言命法」をただ暗記するのではなく、「宗教から理性へと重心が移る啓蒙時代において、絶対的な道徳原理を人間の理性の中に見出そうとした」と理解することで、選択肢の文章の真偽も見抜きやすくなります。
哲学の対比で記憶を強化
思想家の考え方を「対比」させることも有効です!たとえば、功利主義のベンサムとカントの義務論、ソクラテスの対話法とデカルトの方法的懐疑など、対立する考え方を並べて整理すると、理解が深まるだけでなく、記憶にも残りやすくなります。
ノートに「対比図」や「時代順の年表」を自分で書くことも、視覚的に知識を整理するうえで大変効果的です。
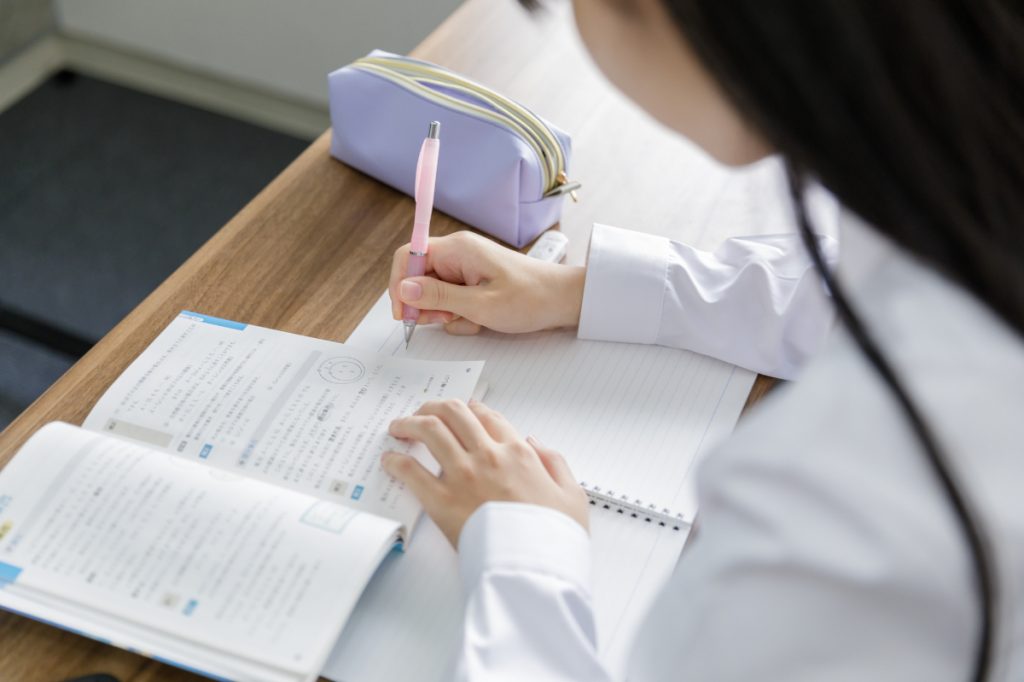
政治・経済の効果的な勉強方法
教科書+資料集を活用した理解の積み重ね
政治経済では、日本国憲法や政治制度、選挙制度、三権分立などの政治の基本的な仕組みに加え、GDP、景気循環、金融政策、国際経済などの経済分野まで幅広く出題されます!
まずは教科書を丁寧に読み、基本語句や制度の意味をしっかり押さえましょう。加えて、資料集に載っている図やグラフ、年表を活用することで、実際の制度がどのように運用されているか、経済指標がどのように推移してきたかなど、具体的な理解が進みます。
時事問題への対応力をつける
政治経済では、特に共通テストや国公立二次試験で「時事的内容」が出題される傾向があります。たとえば「インボイス制度」「マイナンバー」「環境問題とSDGs」「少子高齢化と社会保障」など、ニュースと関連づけて学ぶことで、実感を持った理解が可能になります。
NHKニュースや日経新聞の教育向けまとめ、教育系YouTubeチャンネルなどを定期的にチェックし、時事問題を「試験の材料」として意識的に吸収する習慣を身につけましょう!
私は毎朝ニュースを見ながら朝食を食べることで、時事をキャッチしていました!
倫理と政治経済を組み合わせた学習法
共通するテーマを横断的に学ぶ
「倫理と政治経済は全く別の分野」と思われがちですが、実は共通するテーマやつながりのあるトピックも多くあります。
たとえば、アリストテレスやプラトンの政治思想は倫理と政治分野の架け橋になりますし、マルクスの経済思想は倫理と経済の両方で重要なテーマになります。このように思想と制度の相互関係を理解することで、思考が深まり、記述問題にも強くなります。
教科ごとに役割を決めて暗記と応用を両立
倫理を「用語暗記と文章理解の訓練」、政治経済を「制度や理論の応用練習」として捉えることで、学習にメリハリが生まれます。理解重視の倫理と、知識+実践の政治経済という形でバランスよく進めましょう。



演習と過去問活用のコツ
過去問を分析し「出題パターン」に慣れる
倫理・政治経済の学習で最も重要なフェーズが、過去問演習です。共通テストの過去問を繰り返し解き、出題形式や選択肢のクセ、正答の導き方の「パターン」を体で覚えていきます。
解きっぱなしではなく、「なぜその選択肢が正しいのか/間違っているのか」を自分で言語化して復習することが、得点力向上につながります。
模試や定期試験も活用する
共通テスト形式の模試だけでなく、学校の定期テストや予備校の実践問題集も活用しましょう!形式にとらわれすぎず、知識の穴を早めに見つけて埋めていくことが重要です。特に二次試験を受ける場合、記述式の演習も欠かせません。
モチベーションを維持するために
短期目標を設定する
長期的な受験勉強では、途中で集中力が切れることもあります。そこで、1週間ごとに達成すべき「短期目標」(今週はプラトンとアリストテレスをマスターする、など)を決めることで、進捗の管理とモチベーション維持が可能になります!
他教科とのバランスも意識する
倫理・政治経済は暗記中心の科目といわれますが、それでも理解が必要なポイントは多くあります。他教科と比べて短期間で仕上げやすいため、英語や数学など他科目の勉強時間を確保しながら、効率よく進めることがカギになります!
英語や数学などほかの教科についても記事を書いていますので、よろしければそちらも参考にしてみてください!






応用的な学習法で得点の上限を引き上げる
倫理・政治経済は、基本的な語句や制度を覚えるだけでも一定の得点は見込めますが、共通テストや難関私大、国公立の二次試験では、その先の応用的な理解と判断力が問われる問題が数多く出題されます!したがって、平均点以上の得点を狙うには、単なる暗記を超えた応用的な学習が必要です。
まず重要なのが、「知識の関係性を理解すること」です!
倫理であれば、思想家同士の主張がどのように影響し合っているか、あるいは一つの思想がその後の歴史や社会にどのように応用されたのかを意識して学ぶことで、理解が立体的になります。例えば、アリストテレスの「中庸」の思想が現代の政治哲学や倫理教育にどうつながっているかを探ると、単なる過去の思想ではなく「今と地続きの知識」として記憶されやすくなります。
次に、「具体例をもとに抽象的概念を説明できる練習」も効果的です。
たとえば政治経済で「市場の失敗」という概念を学んだら、実際に環境問題や医療制度など現代社会の具体例を引きながら、その仕組みを説明できるかどうかを確認しましょう。この練習によって、選択問題の読み違いが減り、記述問題でも得点しやすくなります。
さらに、「時事問題とリンクさせる視点」も欠かせません!
倫理では生命倫理や環境倫理、政治経済では財政赤字や少子高齢化、格差社会といったテーマが頻出です。こうしたトピックについて、日々のニュースを見ながら「これはどの単元と関係しているか」「どういう価値観の対立があるか」を考える習慣を持つと、受験本番での対応力が格段に上がります。
また、アウトプット中心の学習も応用力育成には有効です!
選択肢問題を解くだけでなく、自分で問題を作成してみたり、学校の先生や友人とテーマについてディスカッションしてみたりすることで、思考の幅が広がり、知識がより実践的に使えるようになります。
応用的な学習とは、単に難しい問題を解くことではなく、「学んだ知識を活用し、意味づける力」を育てることです。この力は、大学入試はもちろん、その後の大学生活や社会においても大きな武器になります。ぜひ、知識を「活かす」視点を持って、倫理・政治経済の学習をより深く、面白くしていきましょう・・・!
まとめ
倫理・政治経済は「暗記科目」として片づけられがちですが、実は思考力や理解力が問われる重要な教科だと思います!倫理では思想家の考え方をストーリーとして理解し、対比や時代背景から記憶を定着させる。政治経済では、制度や理論を深く理解し、時事問題にも敏感になることで、出題への対応力がつきます!
さらに、倫理と政治経済を単独で学ぶのではなく、テーマごとに横断的に整理し、過去問や模試を通じて実践力を高めていくことが、得点源としての力につながります。
短期目標と学習スケジュールを意識して、継続的に取り組めば、共通テストや難関大学入試でも十分に通用する得点力を身につけることができるでしょう!