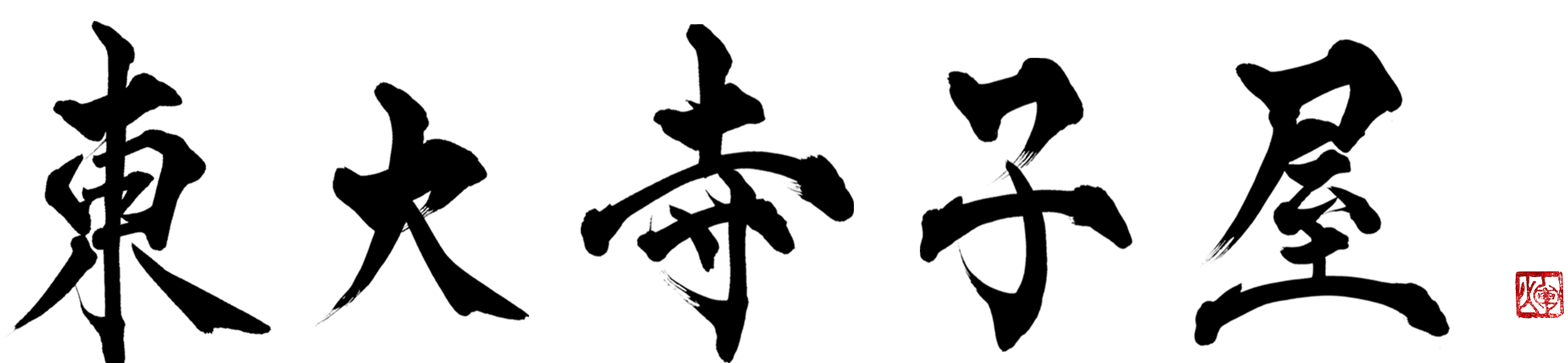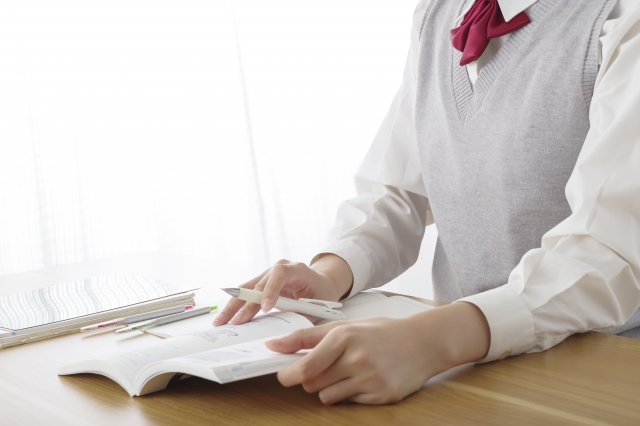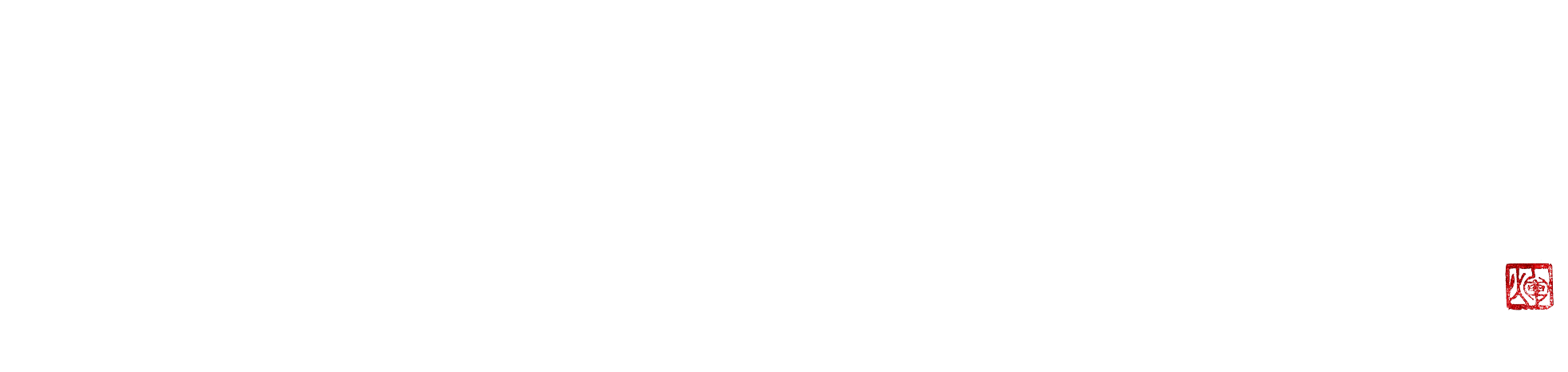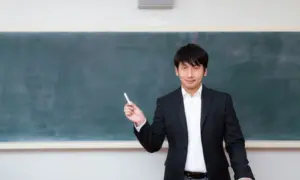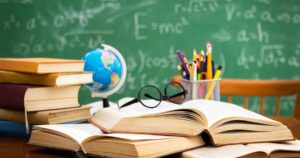はじめに
高校生活は、大学受験や将来の進路に向けて非常に重要な時期です。しかし、「高校生になってどのように勉強すればいいかわからない」「勉強しなければならないのは分かっているけれど、なかなか続かない」「頑張っているのに成績が上がらない」と悩んでいる高校生も多いのではないでしょうか?
勉強を効率的に進めるためには、ただ長時間机に向かうのではなく、自分に合った正しい方法を実践することが大切です!
そこで、この記事では現役東大生ライターのけんけんが、高校生が実践すべき勉強方法や習慣化のコツ、集中力を維持するテクニックについて詳しく解説します!
高校生におすすめの勉強方法
短期・中期・長期の目標を立てる
勉強のモチベーションを維持するためには、目標を明確にすることが重要です!僕も高校1年生の時までは目標を立てず漫然と勉強してしまい、のちのち後悔しました・・・。みなさんはそうならず、目標を立てて勉強をしてみてください!目標には次のような3つの種類があります。
短期目標(1週間~1か月単位)
まず、短期目標はできるだけ達成しやすく設定します。
具体的には、1週間または1か月以内に達成できる目標を立てることです。例えば、「今週中に数学の問題集を30ページ進める」「1週間で英単語を100個覚える」というような、短期間で達成可能な目標を設定することで、やる気が出てきます!
この短期目標を達成することで得られる満足感が次のステップへの意欲を生むため、勉強を継続するためには欠かせません。
中期目標(1か月~3か月単位)
中期目標は少し挑戦的で、今後数ヶ月内に達成できる目標です。
例えば、次の模試で数学の偏差値を5上げることや、定期テストで前回より20点アップさせることなどです。このレベルの目標を設定することで、日々の学習に少しずつハードルを設け、挑戦意欲を持ちながら勉強を進めることができます。
長期目標(1年以上先)
そして、最も重要なのが長期目標です!これには、第一志望の大学・学部に合格するという大きな目標が含まれます。学年の初めに長期的な目標を定め、それに向けて日々の勉強を進めることで、自分が何のために勉強しているのかを常に意識しながら学習することができます。
この目標を達成するためには、計画的に学習を進めることが不可欠です!日々の小さな積み重ねが最終的に大きな結果を生み出します。
学習スケジュールを作成する
計画的に勉強を進めるためには、スケジュールを作成することが大切です!
まず、1日のスケジュールを決めましょう。例えば、朝の時間を英語や社会の暗記に充てることで、昼間の授業で新しいことを学んだ後に復習の時間を確保できます。
そして、放課後には学校での授業内容を復習し、問題演習を行う時間を設けましょう!夜は模試の復習や応用問題に挑戦する時間として活用し、最後に英単語や知識系の科目を暗記します。こうして、毎日の勉強時間を効率的に分けることで、無駄なく学習を進めることができます!
しかし部活などと両立しながら無理のない範囲で学習を進めましょう!勉強が嫌いな方は1日15分からでも始めるとよいと思います!(僕も最初はそうでした・・・)
次に、週単位での学習計画も重要です!
週ごとに「何を勉強するのか」を決めておくことで、毎日の勉強に迷うことなく進められます。例えば、月曜日から金曜日までは毎日違う科目を重点的に勉強し、土日は1週間の復習に充てるといった方法です。週末にまとまった勉強時間を取ることで、今週学んだ内容を確実に復習でき、弱点を早めに把握することができます。
さらに、月単位での振り返りも大切です。毎月「何ができたのか」「何を改善する必要があるのか」を振り返り、次月の計画に生かしましょう。このサイクルを繰り返すことで、自分の進捗を確認し、次の目標に向けてのステップアップを図ることができます。

効率的に勉強するためのポイント
インプットとアウトプットのバランスを取る
「教科書を読むだけ」「ノートをまとめるだけ」では、知識が定着しません。インプット(読む・聞く)とアウトプット(書く・話す)のバランスを取ることが必要です。
まず、インプットは教科書や参考書を使って行いますが、これだけでは情報が頭に残らないことが多いです。そのため、インプットした内容をアウトプットする時間を設けることが重要です。
例えば、数学の問題集を解くことや、英語の文章を自分で作成してみることで、理解度を確認することができます。また、誰かにその内容を説明することも、非常に効果的です。人に教えることで自分の理解が深まりますし、知識がしっかりと身につきます。
また、単に問題を解くだけではなく、「なぜその解法を使うのか?」を理解しながら学ぶことが大切です。理解が深まることで、次回似たような問題が出てきたときにもスムーズに解けるようになります。
スキマ時間を活用する
高校生は授業や部活動で忙しいため、スキマ時間を活用することが重要です。
通学時間や休み時間は、意外に多くの時間を確保できる貴重な時間です。例えば、通学時間に英単語を暗記したり、休み時間に暗記カードをチェックすることで、忙しい日々でも効率的に学習を進めることができます。
通学中に勉強することで、帰宅後に疲れて集中できない時間帯も有効活用でき、時間の無駄を減らすことができます。勉強の隙間時間をうまく活用することで、1日の学習量を増やし、効率よく知識を吸収することができます。
さらに、昼休みや放課後に友達と軽く勉強会を開くこともおすすめです。これにより、お互いに質問し合ったり、苦手なところを教え合うことができ、互いに刺激を与えながら学習が進むことができます。
復習を重視する
「覚えたつもり」ではなく、定期的に復習することで確実に定着させましょう!
復習は知識を長期記憶に定着させるために欠かせません。エビングハウスの忘却曲線を活用し、復習のタイミングを決めると効率よく覚えられます。例えば、1日後、1週間後、1か月後に復習することで、記憶が定着しやすくなります。
このサイクルを意識して学習を進めることで、短期的な記憶だけではなく、長期的な記憶も保持しやすくなります。
また、復習の際には、過去に解いた問題や模試の解答を再度確認することが有効です。間違えた問題をもう一度解き直すことで、自分の弱点を克服することができます。
勉強を習慣化するコツ
ルーティン化する
毎日同じ時間に勉強を始めることで、「勉強するのが当たり前」という習慣を作ります!
まず、勉強する時間を決め、その時間には必ず勉強を始めるようにします。例えば、「毎晩10時から1時間は必ず勉強する」と決め、最初は少しの時間からでも始めましょう。最初は短時間でも、続けることでだんだんと勉強をする習慣がつきます。
さらに、勉強をルーティン化する際には、前もって勉強する科目を決めておくとスムーズです。例えば、平日は英語と数学、土日は復習といったように、曜日ごとにやることを決めておくと迷うことなく学習が進みます。
モチベーションを維持する工夫
勉強を習慣化しても、途中でモチベーションが低下することがあります。
そのため、自分がやる気を出すための工夫を取り入れることが大切です。例えば、勉強後に自分へのごほうびを設定することが効果的です。「1時間勉強したら10分休憩を取る」などの小さなごほうびで、モチベーションを維持できます。また、好きな文房具を使うことや、勉強仲間と競い合うこともモチベーションアップに繋がります!
例えば、「次のテストで負けない!」という気持ちを持つことが、勉強を続ける原動力になります。
環境を整える
勉強に集中するためには、環境を整えることが不可欠です。集中できる場所で勉強することが重要であり、スマホの通知や他の誘惑を減らすことが効果的です。
例えば、スマホは手の届かない場所に置くか、勉強する部屋に持ち込まないようにしましょう。学校の自習室や図書館の静かな場所で勉強することも有効です。また、勉強机の上は常に整理整頓しておき、余計なものが視界に入らないようにすると集中しやすくなります。



まとめ
高校生が勉強を効率的に進めるためには、正しい勉強方法を身につけ、習慣化することが重要です!
短期・中期・長期の目標を立て、計画的に学習を進めることで、成績向上につながります。また、インプットとアウトプットのバランスを意識し、スキマ時間を活用することで、限られた時間の中でも効果的に勉強できます。
さらに、勉強を習慣化するためには、ルーティン化やモチベーション維持の工夫が必要です。自分に合った方法を見つけ、継続的に学習を続けることで、志望校合格や成績アップを目指しましょう!