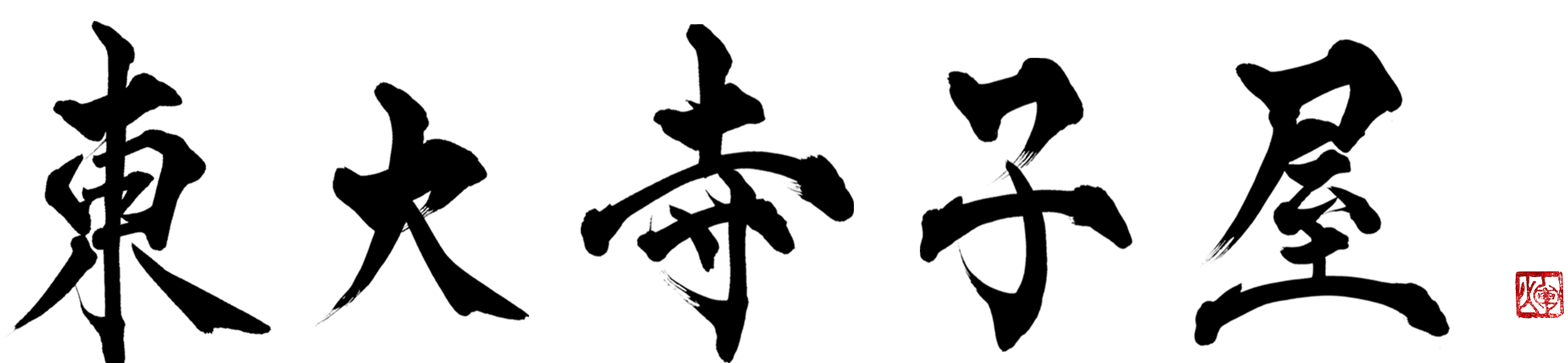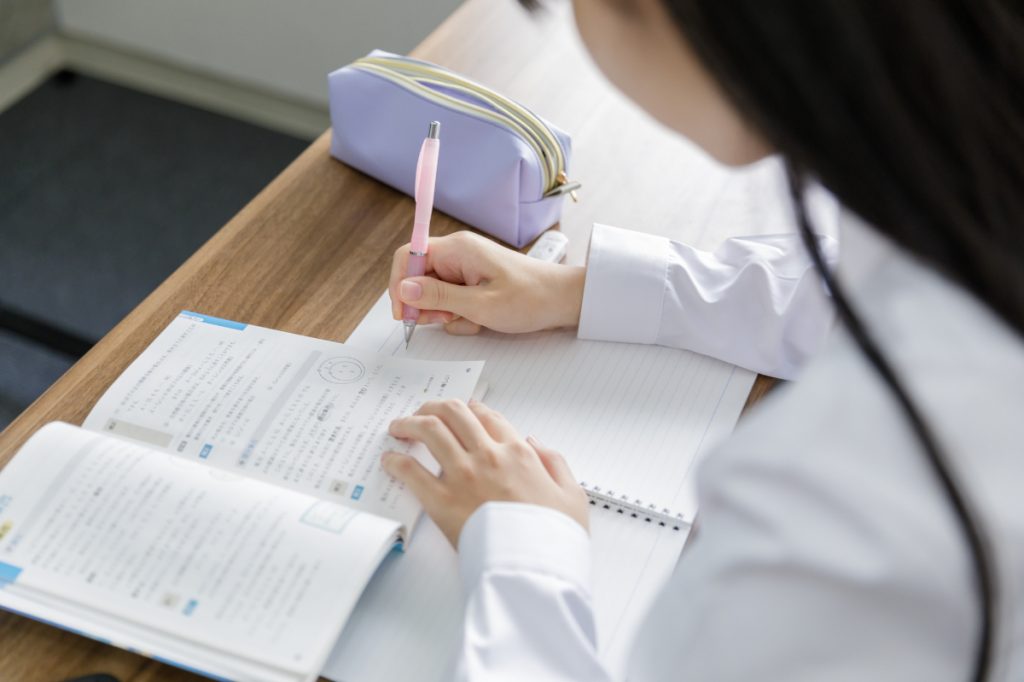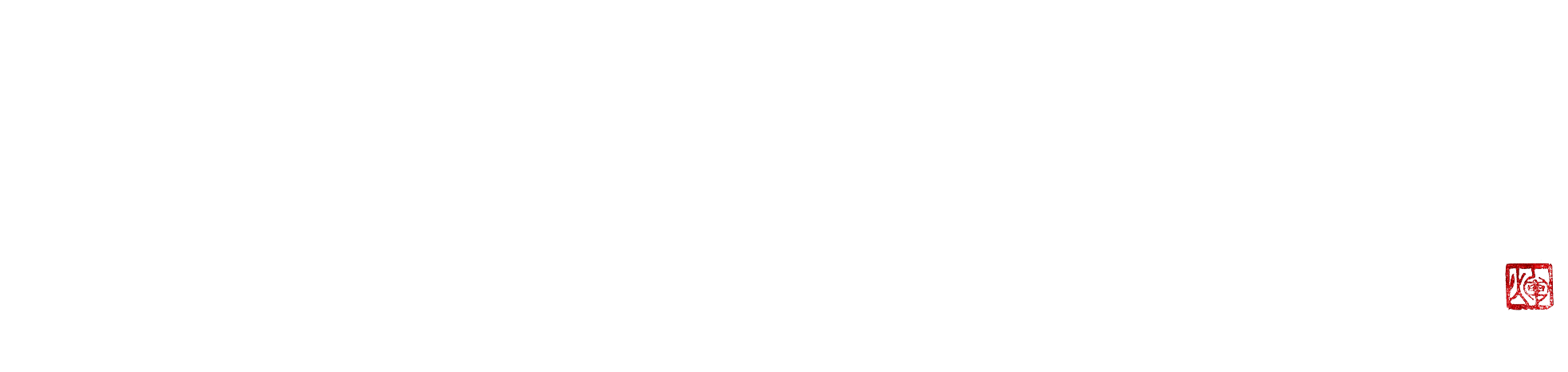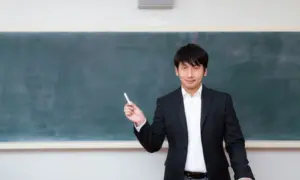こんにちは。東大寺子屋という塾で講師をしている、現役東大生のみーみーです。この春から中学校にご入学された皆さん、おめでとうございます。期待や不安が入り混じっていると思いますが、一度きりの中学校生活を楽しんでください!
さて、中学生になると、多くの新入生が最初にぶつかる壁が「定期テスト」です。小学校ではあまり意識することがなかった「テストの順位」や「内申点」が、急に重要な意味を持ち始めるのが中学校の世界。しかも、授業の進みも速くなり、教科も増えるため、勉強への取り組み方そのものが大きく変わります。

私も中学校に入った直後は、学校の勉強についていけるかどうか、テストで悪い点を取ってしまわないか、とても不安でした。定期テストの勉強の仕方もわからないし、そもそも授業をどうやって受けたら良いかもわかりませんでした。
というわけで、この記事に辿り着いた中学1年生の皆さんはラッキーです。最後まで読めば、初めての定期テストを受ける不安が解消されると思います!
中学生活のスタートを切ったばかりの新入生にとって、最初の定期テストは今後の学習習慣を左右する大切な機会です。この記事では、中学生の新入生が初めてのテストで良い結果を出すための具体的な勉強法や心構え、注意点などを詳しく紹介していきます。
中学生になって変わる「テスト」の意味
小学校との違いは?
小学校のテストは単元ごとの確認が中心で、範囲も狭く、点数がそのまま成績に直結するわけではありませんでした。しかし中学校に入ると、中間・期末テストという「定期テスト」が導入され、評価に直結するようになります。
テストの結果は通知表に反映され、通知表は高校入試の「内申点」として記録されるため、1年生のうちからテストの点数は非常に重要です。
最初のテストが大切な理由
最初のテストで良い成績を取ると、本人の「やればできる」という自信に直結します。逆に、初回のテストで失敗すると、苦手意識が芽生え、その後の勉強へのモチベーションにも悪影響が出る可能性があります。
ただ、本当に勉強ができるようになるためには、失敗・挫折することも大切です。いつも何をやってもうまくいく人なんてほとんどいません。
本当に大切なのは、テスト勉強がうまくいかなかったとしても、諦めずに原因を分析し、次の定期テストではいい点を取ろうという粘り強さを持つことです。
テスト勉強はいつから始めるべき?
テスト勉強の開始時期は、一般的にテストの2週間前が目安です。中学校によっては、学校側から「テスト範囲表」が配られることがありますので、それを受け取った時点から計画を立て始めましょう。
なぜ2週間前から?
中学の定期テストは、5教科以上(英語・数学・国語・理科・社会)で出題範囲も広いため、短期間で一気に覚えるのは難しいです。また、暗記科目と理解が必要な教科のバランスを考えると、余裕をもって勉強を始めることが高得点の鍵になります。
入学してすぐ、とかテスト3週間前から始めるのはそこまで意味がありません。入学直後は周りの人と仲良くする、部活に入るなど様々なイベントを大切にしてほしいですし、3週間前から始めても、モチベーションが続きません。



逆に、1週間前から始めるのでは遅すぎます。基本的にテスト勉強は2,3周するのが前提なのですが、1週間しかないとテスト範囲を1周するのが精一杯で、日々の授業を相当しっかり受けていないと、内容を定着させられないままテストをうけることになります。
教科別・新入生向けおすすめ勉強法
英語:新しい言語は「毎日コツコツ」
中1英語は基礎の基礎。最初のうちに文法や単語をしっかり身につけておくことで、後々の学習が楽になります。
- 単語は1日10個程度、音読しながら書いて覚える
- 文法は教科書やワークで繰り返し演習
- リスニングの対策も忘れずに
数学:計算ミスをなくすには「書いて解く」しかない
中学の数学は「文字式」や「方程式」など抽象的な内容が増えてきます。理解できた気になっても、実際に解いてみるとできないことがよくあります。
- 問題演習を中心に、手を動かして覚える
- 解き方をノートにまとめて復習
- 解き直しノートを作ってミスの傾向をチェック
国語:読み取り+漢字はバランス良く
- 教科書本文の音読と要点まとめ
- 漢字練習は毎日少しずつ
- 定期テスト前に問題集で読解練習
理科・社会:インプット&アウトプットの繰り返し
- ノートを使って図や表を整理
- ワークや問題集で知識を確認
- 一問一答で暗記チェック
効率的な勉強スケジュールの立て方
新入生がよくやりがちなのが、「やる気はあるけど何からやればいいかわからない」という状態。まずは1週間単位のスケジュールを作り、毎日のタスクを明確にしておきましょう。
2週間前:インプット中心(教科書・ノートの見直し)
- 1日2教科を目安に復習
- 苦手な単元に時間を多めに配分
1週間前:問題演習中心(ワーク・問題集)
- 教科書ワークを1周終わらせる
- 間違えた問題をノートにまとめておく
3日前〜前日:総復習と暗記チェック
- 一問一答形式での確認
- 英単語・漢字・年号などを総復習
- 前日は早めに寝てコンディション調整
新入生が注意すべき落とし穴
「直前に詰め込めば大丈夫」は危険!
中学の内容は範囲が広く、直前だけで点数を取るのはほぼ不可能です。少しずつ、毎日コツコツが一番の近道です。
スマホ・ゲームの誘惑に注意
特にテスト期間中はスマホの使用時間に注意。通知をオフにする、勉強中は親に預ける、時間を決めるなど、自分でルールを作ることが大切です。
家族との連携もポイント
中学生になると、自立が求められますが、家庭のサポートも欠かせません。
- 学習状況を家族に報告する
- 勉強スケジュールを共有する
- 食事・睡眠・生活習慣の安定
最初のテストで成功するための心構え
最後に、新入生として初めてのテストに臨む際に、ぜひ心に留めておいてほしいことをまとめます。
- 完璧を目指さなくていいから、ベストを尽くすこと
- 結果に一喜一憂せず、次につなげる姿勢を持つこと
- ミスを恐れず、復習のチャンスだと捉えること
大事なのはテストを受けたあと
初めての定期テストはどれだけ綿密に準備したとしても、予想とは違った出題がされたり、難しい問題が出されたりします。その結果、思ったような結果を出すことができないことがあるかもしれません。
しかし、2回目以降の定期テストに向けて勉強の仕方を修正することができますし、先生がどんな形式でテストを出すのかを掴むこともできます。そのため、初めての定期テストは実験のようなものだと思っても良いかもしれません。
私も初めての定期テストでは勉強の仕方がわからず、あまりいい点を取ることができませんでしたが、弱点を分析・修正して次の定期テストでは学年の上位に入ることができました。
まとめ
中学生活はまだ始まったばかり。最初のテストで緊張するのは当たり前ですが、計画的に準備を進めていけば、結果は必ずついてきます。
テストはゴールではなく、通過点です。この経験を通じて、自分の勉強スタイルやペースをつかみ、継続する力を身につけていきましょう。
「できるか不安…」と思う新入生こそ、今から少しずつ準備を始めてみてください。それが、3年後の受験への第一歩になります。
学校の勉強についていけるか不安、定期テストに向けた勉強の仕方についてもっと知りたい、という方は、ぜひ一度東大寺子屋の体験授業を受けてみてください!無料で現役東大生に相談することができます。
皆さんが定期テストを乗り越えて楽しい中学校生活を送ることができるのを願っています!