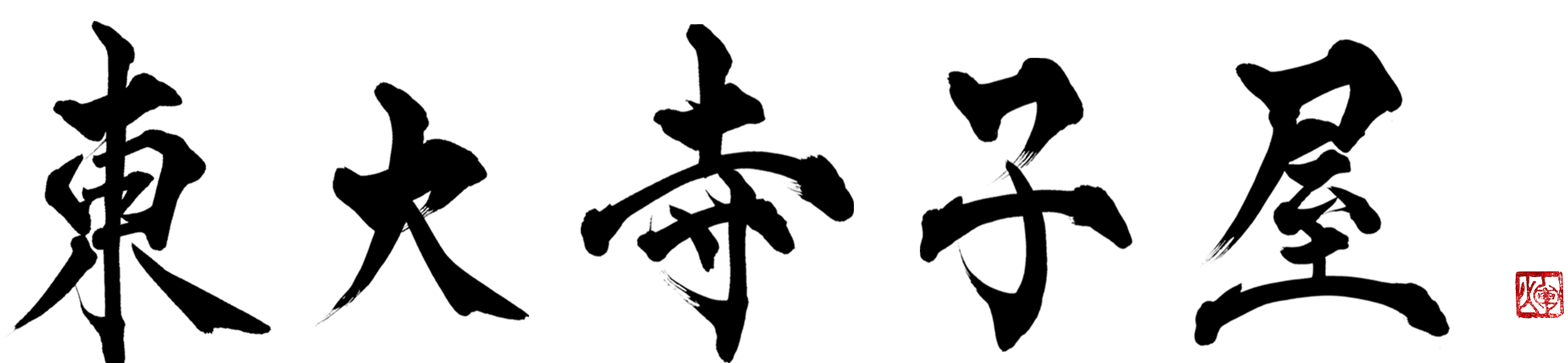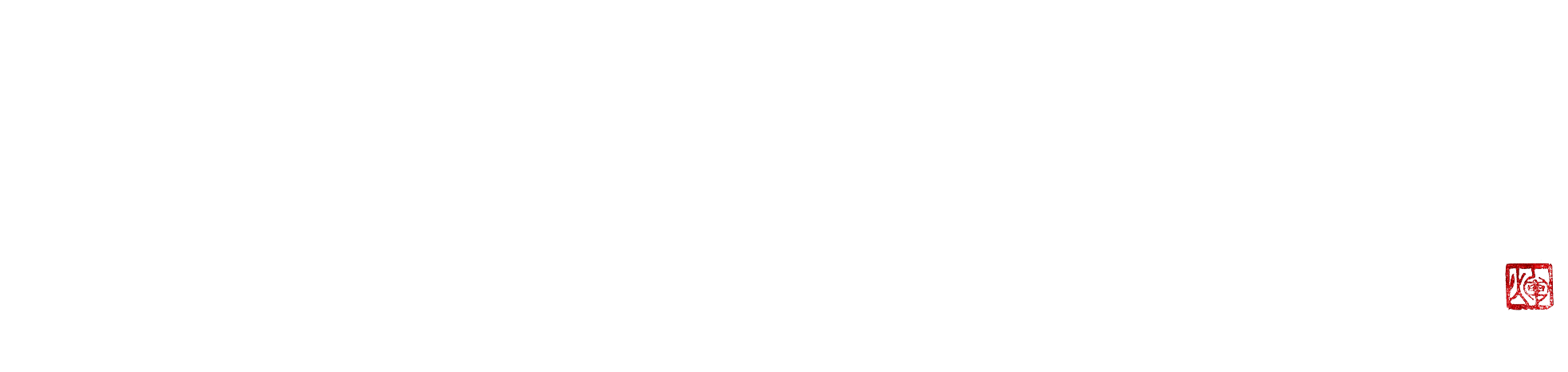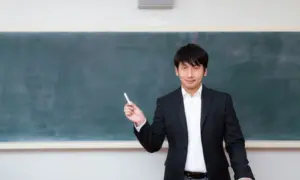はじめに:古文・漢文は「言語」であると理解する
古文と漢文。この2つの科目に対して「意味がわからない」「暗記ばかりでつまらない」と苦手意識を持っている高校生は少なくありません。
現代語とは文法や語彙が大きく異なるため、「読むだけで疲れる」「何を言っているのか分からない」という声もよく耳にします。実際私も暗記が苦手なのでこの科目に取っつきにくい印象を受け、勉強するのに気後れしていました・・・。
しかし、古文や漢文は、正しいアプローチと手順を踏めば、確実に得点源に変えることができる科目です!実際、難関大学に合格した受験生の多くは、古文・漢文を安定して得点することで、他の受験生と差をつけています。
そこでこの記事では現役東大生ライターの「けんけん」が、「古文・漢文を苦手から得意へ変える勉強法」を、初心者でも取り組みやすいよう段階を追って詳しく解説します!
古文の勉強法:基礎を固めて読解力へつなげる
古典文法の徹底理解
古文を読むためにまず必要なのは「古典文法」の知識です。これは現代文と同じ感覚で読んでいては理解できない理由のひとつです。助動詞、助詞、活用、敬語法、係り結び、打消しの接続など、一定のルールに従って文章が構成されているため、最初にこのルールを覚えない限り、文全体の意味が取れません。
助動詞については、接続・意味・活用・識別の4つをセットで覚えることが重要です。たとえば「けり」は連用形接続で過去・詠嘆を表す助動詞ですが、単に「けり=過去」とだけ覚えてしまうと、文脈によって意味を誤る可能性が出てきます。接続の違いや用法をしっかり理解することが、古文読解の第一歩です!
また、活用表を空で言えるようにし、助動詞が文中でどのように使われているのかを瞬時に見分けられるようにすることで、文章を読むスピードも理解力も格段に上がります。
語彙力を高める:古文単語の習得法
古文単語は現代語とは意味が大きく異なるものが多く、直訳しても意味が通じないことが頻繁にあります。そのため、古文単語帳を使って頻出語を100〜200語は確実に押さえましょう!私は古文単語をないがしろにしてしまい点数が安定しない時期がありました・・・。
単語の暗記では、ただ意味だけを覚えるのではなく、語感や例文を通してイメージで覚えることが大切です!
たとえば、「あはれ」は「しみじみとした感情」全般を表す多義語ですが、その微妙なニュアンスを例文で繰り返し確認することで、文章中でも自然と意味が取れるようになります。
また、似たような意味の単語をグループ化したり、反対語をセットで覚えると、記憶の定着が高まりやすくなります。暗記は反復が命です。定期的にテスト形式で復習しながら語彙力を増やしていきましょう。
音読と品詞分解で読解力を鍛える
古文読解において有効な方法が「音読」と「品詞分解」です。音読は、古文特有のリズムや助詞の使い方を体で覚えるのに非常に効果的です。古典の言葉は、繰り返し口に出すことで慣れが生まれ、読解スピードや理解度も上がります。
品詞分解は、文章中の語を一つひとつ文法的に分解して分析する作業です。これによって文構造が明確になり、助動詞や敬語の役割も把握しやすくなります。
毎日1問でも構わないので、品詞分解→現代語訳→内容把握のプロセスを繰り返していくと、自然と文章を読む力がついてきます。

漢文の勉強法:構文と語法を徹底的に押さえる
返り点のルールを理解する
漢文読解でつまずく最大の理由は「返り点の読み方が分からない」という点に尽きます!漢文には独自の読み下しルールがあり、「レ点」「一二点」「上下点」などがその典型です。これらは文の構造を決定づける非常に重要なサインですので、まずはそれぞれのルールを正確に覚える必要があります。
たとえば、「之ヲ愛ス」という構文であれば、「之(これ)」「ヲ(目的格助詞)」「愛ス(動詞)」というように、返り点を元に語順を日本語に直す必要があります。このプロセスに慣れていくことが、漢文読解の第一歩です。
句法の暗記と活用
漢文には頻出する「句法」があり、それぞれ決まった訳し方が求められます。「使役」「受身」「否定」「反語」「仮定」「比較」など、漢文独特の構文には特有の読み方があります。例えば「使A〜B(AにBさせる)」という構文では、使役のニュアンスを正しく読み取る必要があります。
句法の知識がないと、漢文はただの漢字の羅列にしか見えません。句法を体系的に暗記し、実際の文の中でどう使われるかを確認していくことが重要です!問題集や教科書の例文を何度も書き写したり、音読したりすることで、定着が早まります。
語彙力と頻出漢字の読み
漢文では語彙力も大切です。特に動詞・名詞・副詞など、使用頻度の高い語を中心に暗記しましょう。たとえば「臣=わたくし」「君=あなた」「天下=世の中」など、基本的な言葉を正確に理解していないと、全体の文脈がつかめません。
また、同じ漢字でも文脈によって意味が変わる場合があります。たとえば「子」という字は、「こ(子ども)」「し(あなた、君子)」「ね(十二支)」といったように、文脈によって意味が変化します。例文と一緒に覚えると理解が深まります。
共通テストや難関大入試への対応
古文・漢文を得点源に変えるためには、基本的な知識や読解力の習得だけでなく、入試本番で求められる「実戦的な対応力」を身につけることが重要です!特に共通テストや難関大学の入試問題では、単なる語彙や文法の知識以上に、「文章全体を把握する力」や「設問の意図を読み取る力」が問われます。
共通テストの古文・漢文では、比較的平易な文章が使われることが多いものの、設問が細かく論理的であり、本文との対応関係を正確に把握しないと正解を導き出せません。そこでまず大切なのが、「文章を一文ずつ丁寧に訳し、場面ごとの内容を的確に押さえること」です。これを怠ると、設問を読み違えたり、本文の重要な情報を見逃したりする原因になります。
たとえば古文であれば、登場人物の関係性や心理の変化、敬語表現による上下関係などに注目し、物語の流れをつかむ力が必要です。漢文では、句法の識別と文構造の読み取りに加えて、詩文の主題や筆者の意図を汲み取る読解力が求められます。
難関大学の入試問題では、古文・漢文のレベルが一段と高まり、文脈依存の表現や高度な敬語、漢詩や古典随筆など文学的素養が問われることも少なくありません。そのため、日頃から「難解な文章にも触れておくこと」「現代語訳を自分の力で行う訓練を積むこと」が不可欠です。単なる暗記ではなく、背景知識や文学的文脈を意識しながら読む姿勢が、入試本番での得点力につながります。
さらに重要なのが、「問題演習→復習→分析」のサイクルを継続して行うことです。過去問や模試の問題を解く際は、間違えた問題の解説を熟読するだけでなく、「なぜ間違えたのか」「どの知識が不足していたのか」を明確にし、次に同じタイプの問題に出会ったときに正解できるよう対策を練っておくことが必要です!
時間配分の感覚を掴むことも忘れてはなりません。共通テストでは、時間に対して設問数が多く、じっくり考えている時間はありません。そのため、過去問演習や予想問題を活用して、時間内に全問解き切るトレーニングを積むことが、実力を安定して発揮する鍵となります。
総じて、古文・漢文の入試対応には、知識の土台を固めたうえで、実戦的な読解演習を重ねることが極めて重要です。「読む力」と「解く力」の両輪をバランスよく鍛えながら、共通テストや難関大学の入試に備えましょう!



まとめ:古文・漢文は繰り返しで必ず伸びる
古文・漢文は、暗記と論理のバランスを取りながら勉強することで、確実に得点源に変えることができる科目です!最初は取っつきにくく感じるかもしれませんが、毎日少しずつでも継続することで、読解力も知識も着実に伸びていきます。
古典文法・句法を基本から固めること。語彙力を徹底して強化すること。そして何より、読み慣れること。これらのステップを順に踏んでいけば、古文・漢文は「得意科目」へと変わっていきます。
受験において古文・漢文は他の受験生が油断しやすいポイントでもあります。だからこそ、ここを徹底して強化すれば、大きなアドバンテージになります。今日から正しい勉強法で、着実に力をつけていきましょう・・・!
また、現代文など他の教科についても記事を書いているので困っていたらそちらもご参考ください!